私たちの取り組む課題



1.子ども・学生の孤立と“居場所の分断”
家庭・学校・地域という三つの場のどこにも安心できる場所がないまま、
孤立していく子どもや学生が増えています。
学校へ行けない、教室に入れない、進路や将来に希望を持てない——
そんな声が日々寄せられています。
2.支援の“つなぎ目”の欠如
教育・福祉・医療などの制度の間にある“隙間”にこそ、
支援が必要な子どもや家庭がいます。
一方で、複数の機関を渡り歩くことに疲れてしまい、
「どこに相談すればいいのか分からない」という現実もあります。
当法人は、こうしたつなぎ目を埋める「相談と伴走の場」を担っています。
3.学生・若者支援の不足
地域には、学び直しや社会参加を支援する仕組みがまだ十分に整っていません。
私たちは大学生や若者がボランティアとして関わり、
“支援される側”から“支える側”へと成長できる場づくりを行っています。
この循環こそが、地域における自立と共生の基盤になると考えています。
4.保護者の孤立と情報格差
不登校・発達特性・生活困難などの背景を持つ家庭では、
保護者がひとりで悩みを抱え込み、支援制度を活用できないことがあります。
当法人は、保護者が安心して相談できる場を設け、
必要な情報を共有しながら“共に考える支援”を行っています。
5.地域全体の共助力の低下
子どもや若者を支える力が家庭や学校だけに偏っており、
地域が支援に関わる仕組みが弱まっています。
私たちは、学生・地域住民・企業・行政が協働し、
「子どもにやさしいまち」を育てるネットワークづくりに取り組んでいます。
なぜこの課題に取り組むか
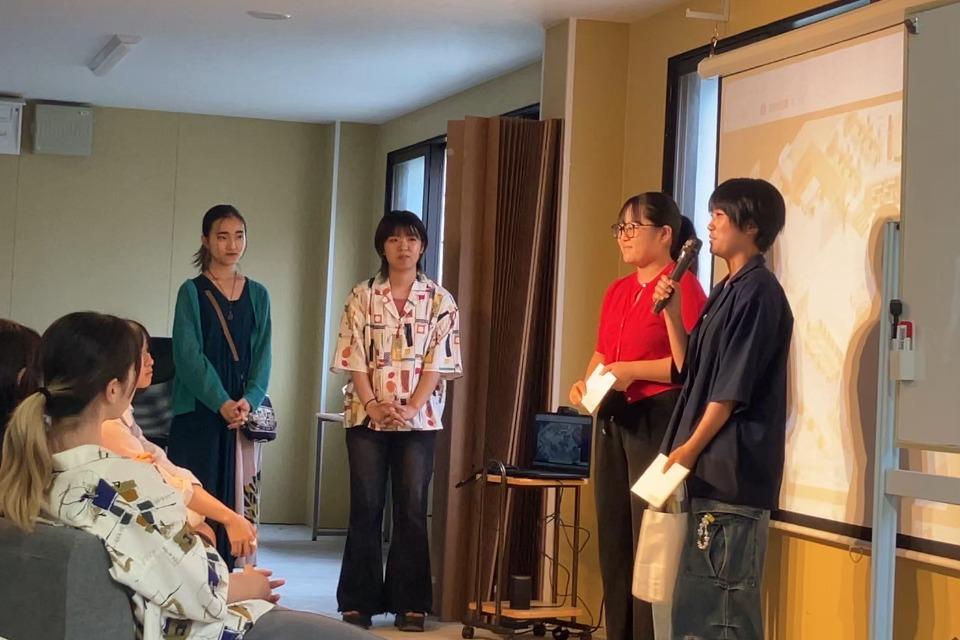


近年、非行・自殺・不登校など、さまざまな背景を抱える学生が増えています。
社会的な要因が学生の心や生活に大きく影響しているにもかかわらず、
そのような子どもたちに社会の目が届きにくい現実があります。
プライバシーや制度の壁により、問題を「見えないもの」にしてしまう社会のあり方にも危機感を抱いています。
学校に行けなくなったことや、命を落としたことさえ、
周囲が深く気に留めないまま過ぎていく——。
そんな状況の中で、学生たちがどのように自分を認め、社会とつながっていけるのか。
私たちはこの問いに真正面から向き合いたいと考えています。
真面目で素直な学生が多く、疑うことを知らずに我慢し続けてしまう。
苦しみながらも、どう向き合えばいいのか分からずにいる子がたくさんいます。
だからこそ、学校や家庭だけでなく、地域の中にも「教え、支え合える関係」が必要です。
地域だからこそ伝えられる、人との関わり方や社会的なルール、助け合いのあり方があります。
学生が早い段階で、自分の身の回りの出来事に向き合い、
ため込まずに言葉にできるようになること。
そして、自分も相手も大切にできる力を身につけること。
それが、不登校や自殺、犯罪などのリスクを減らし、
安心して生きていける社会の基礎になると考えています。
私たちだけでは解決できないからこそ、地域全体で子どもと学生を支え、
共に学び合いながら取り組んでいける仕組みを広げていきたいと考えています。
支援金の使い道



1.居場所の運営費
- 光熱費、家賃、通信費など、日々の運営にかかる基本経費
- 子どもたちが安心して過ごせる空間づくり(家具・備品・書籍などの整備)
2.学習・生活支援
- 学習教材やICT機器の購入
- 学び直しや進路相談など、学生の「やりたい」を応援する活動経費
- 食事やおやつの提供、食材費などの生活支援
3.学生スタッフ・ボランティアの活動支援
- 学生ボランティアの交通費・活動費
- 若者が社会参画するための研修や交流活動の実施費用
4.地域との連携・イベント運営
- 「ところティーンズフェスティバル」など、学生と地域がつながる企画運営費
- 学校・企業・行政などとの協働活動の準備・広報費
5.支援を必要とする子ども・家庭への直接支援
- 相談対応、同行支援、物品支援など、家庭の状況に応じたサポート
- 専門機関との連携・情報提供・ケース対応などに伴う費用


