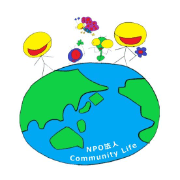フィリピンの貧困率は15.5%(2023年)、徐々に改善されつつあるも貧富の格差は依然と大きい。Aちゃん(小6)は、障がいのあるお姉ちゃんとお母さんとの3人暮らし。お父さんはマニラで日雇いの出稼ぎをしながら、毎日400ペソを家族に送金している。月25日労働として10,000ペソ、現在のレートで約27,000円程度である。そしてオフィス街にある都市部のカフェに入り、アイスカフェラテとブルーベリーチーズケーキを注文すると600ペソ。おしゃべりを楽しむ人たちで賑わっている。経済発展の狭間で暮らす子ども達が健やかに育つように・・・。
Story
~Community-FriendlyなNPOを目指して~
Friendlyという言葉が好きで、平成23年3月に開所した障がいのある子どものデイサービスを「フレンドリー」に決めた。初めて来てくれたのは3歳の女の子、嬉しくて今でも覚えている。「ピンポーン」と呼び鈴が鳴り、玄関先に立つ両親に駆け寄る。ふっと目を落とすと、母親の腕に抱かれている黒目勝ちの小さな瞳がぼんやりと宙を見つめていた。ローラー滑り台の公園までよちよち歩き、ぎこちなく鉛筆を握りひらがなを一緒に書いた。ビート版を胸にギュッと抱えてキャッキャッと泳ぎ、「一人で帰る」と言ってバスの練習を頑張った。あっという間に15年がたち、今年度高校を卒業する。その間、様々な子どもたちと出会い、そして一人一人大切に関わってきた。
Friendlyには友好的なという意味の他に「User-friendly computer (ユーザーに優しい:使いやすいコンピューター)」や「Environment-friendly society(環境に優しい社会)」「Child-friendly facility(子どもが使いやすい施設)」などといった表現で使われる。様々なFriendlyさがあり、それだけ生きづらい社会になっているのかとも感じる。そして今、私たちは地域に優しい「Community-Friendly」なNPOを目指している。現在の地域社会には多様な人たちが暮らし、さらに個別化が進んでいる。一人でも生きていける環境・制度が整う一方、孤独・さみしさなどの精神的な不自由さは募る。地域が急速に多様化していくにもかかわらず、社会構造や慣習はなかなか変わらず、本流から外れてしまう人たちもまた多様化し地域に点在している。私たちがこのような多様な人たちへの支えとなるためにも多様なニーズに立ち向かい、SDGs「Leave no one behind(誰一人取り残さない)」、その一人に必要な私たちでありたいと思っている。

▼私たちの活動について
以下の活動を行っている。
①障がいのある子どものためのデイサービス「フレンドリー」の運営
②外国人のためのソーシャルワークサービス/外国ルーツの子どもの学習サポートの実施
③子ども食堂「みんなでCooking」の開催
④生きづらい若者が学び直しできる「夜間教室」の運営(令和6年3月19日愛媛新聞記事)
⑤国際理解教育:学校訪問や国際交流イベント(多文化Cooking:令和5年6月29日愛媛新聞記事)
⑥フィリピンに子ども食堂を広げようプロジェクトの実施
一つの領域に特化していくのではななく、多領域に関わっていくことで対人支援全般を担い、地域の問題解決を目指している。例えば、増加する外国人の家族に障がいのある子どもがいる、デイサービスで得た知見を家庭支援に生かす、不登校等を経験した夜間教室の生徒から今の子ども達の支援を考えていく、フィリピンの活動を学校の授業に生かしていくなど、複合的な課題感をもって地域活動を実践している。
▼フィリピンでの活動について
私たちがフィリピンと関りを持つようになったのは、平成28年から約3年間JICA草の根支援事業で障がい児者支援に携わったことから始まる。フィリピン・ロドリゲス市の障がい児者宅の訪問リハビリや支援者対象のトレーニング、現地関係者を松山市に招聘して研修などを行った。プロジェクト終了後も繋がりをもって活動していたが、突然のコロナ禍で全てが止まった。
一方、松山市において、私たちは令和3年6月から月1回のペースで子ども食堂を始めた。10人程度の少人数で、みんなでお料理して一緒に食べている。行動制限がありながらも楽しい時間を過ごしていった。小さいフードパントリーも整え、必要な人に届くようにデイサービスで培った福祉的なネットワークを活用、そして昨年からは社会福祉施設でも活動するようになった。徐々に松山市にも子ども食堂が増え、その形態も多様化し、今ではなくてはならない地域資源になっている。
日本のような子ども食堂がフィリピンでもたくさんあればいいのに、という思いがあった。経済発展著しいフィリピンだが、その貧富の格差は大きく、さらにコロナ禍とインフレ下で拍車がかかり、栄養不足の子どもたちが増えてきている。できることをしようと現地スタッフから提案があり一昨年にマニラ市のスラム地区で給食プログラムを始める。毎回たくさんの親子が来た。幼い子ども抱えた母親の後ろをタッパを胸にパタパタついてくる女の子、少し大きめのスプーンで口いっぱいに食べる男の子。現地行政も協力的になり、地元の会社からの寄付も頂けるようになった。

~フィリピンに子ども食堂を広げようプロジェクト~
現在は、ロドリゲス市で活動している。JICA草の根支援事業の際に「サマバカモ」という障がいのある子どもの親の会と出会った。福祉制度が整備されていない中においても、障がいのある子どもとともに明るく地域で活動する姿に感銘を受け、現在まで協働関係を継続している。
一昨年前から、障がいのある子どもだけでなく、地域の子どもたちも含めて給食プログラムを開始。土曜日のみの実施であるが、徐々に子どもたちの数は増えてきた。障がいなどで外出自体が難しい子どもには宅配活動も実施している。食事等の準備は「サマバカモ」のお母さんたちと障がいのある青年たち、最近は子どもたちもお手伝いをしてくれている。障がいのある青年たちは責任感を持って取り組み地域に貢献できている自信を持ち始め、そして何よりも子どもたちは毎週土曜日を楽しみにしている。

▼子どもたちに温かい食事と学ぶ機会を
ある土曜日の朝早く、まだ食事の準備も取り掛かっていない時間に小さな男の子が来た。どうもお腹が空いているらしい。昨晩からあまり食べておらず、たまたま早めに来ていたボランティア(障がいのあるお兄さん)が近くのショップでパンを買ってあげたようだ。これは例外でない。この地域は貧しい家庭が多い。ある家庭では両親と4人の子どもが暮らし、父親は日雇いの大工で仕事は不定期、1日働いて1000円にも満たない。学校に行くためにはバイクタクシー代、学用品代などお金がかかる。それほど大きな額ではないが、彼らにとっては大きな額なのである。その為学校には行けない状態が続き、知らず知らず日々過ごしているうちに教育格差が生まれてきている。
食事の前に学習活動を始めた。字を知らない、数が分からない。それでも成長していく、大人になる。学ぶことはこれから未来に進んでいくために必要なものであり、そして「決して盗まれることのない無形の財産である。」これは私たちの給食プログラムに参加している女の子の家を訪問した際におじいさんが言った言葉である。彼女に両親はおらず、おじいさんが育てている。家の外観だけで彼女の境遇が分かる。しかし暗さは感じない、笑顔がかわいい。おじいさんの収入は不定期だが学校には頑張って通わせている。その他幼い弟妹もいる。私たちの給食プログラムに本当に助けられているとも言ってくれた。

▼給食プログラムは最良の子ども支援
これまで約3年間給食プログラムを実施してきた。子ども一人一人に違うバックグラウンドがある。それは当たり前であるが何故か見過ごされ、無意識に一括りにしている。「栄養不足の子ども」一人一人には愛情深い家族がいて、やってみたいこと、憧れる職業、楽しい思い出、つらい経験がある。どんな日常を送っているのか、そしてどんな未来が待っているのか。一人一人に思いを馳せ、楽しみにしている子どもが今の原動力となっている。
子ども支援に関する国際協力の活動は多岐に渡る。家族や地域の自助努力を促していくものや、私たちのような子どもに直接支援していくものなどがある。家族が子どもを適切に育てられるようにサポートしていくには地道な支援と一定の期間は必要で、2-3年はかかってしまう場合もあり、そしてどうしても不確実性が付きまとう。大人にとってはたった2-3年に、子どもは1年生から3年生になる。子どもの成長スピードは早く、大人の時間はあっという間に過ぎる。一食一食ではあるが、子ども達の育ちに確実に役立ち、それを直接子どもたちに提供できる給食プログラムは最良の子ども支援だと感じている。

~今後の活動について~
出来限りこの給食プログラムを継続していきたい。これは「与える援助」ではなく、「子どもの人権」を守る大人の義務である。私たちの活動が拠点となり、様々な地域で始まっていくことを願っている。現在は毎回25-30人の子ども達が来ている。場所が手狭で今の人数から増やすことは難しいが、私たちの活動が地域社会に認められ少しずつでも広がっていくことを願っている。
国内外で関わる一人一人を丁寧に関わることを理念とし、これまで歩んできた。私たちは資金的に潤う代わりに、たくさんの子ども達の笑顔で満たされてきた。子ども達や家族が「当てにしてくれている」実感がある。多くのNPO法人は財政的に不安定で善意で支えられている場合が多いが、行政等の支援が届かない人たちにとっては大切な社会保障である。それを絶やさずに次の若い世代へと繋いでいきたい。