Issues we are working on
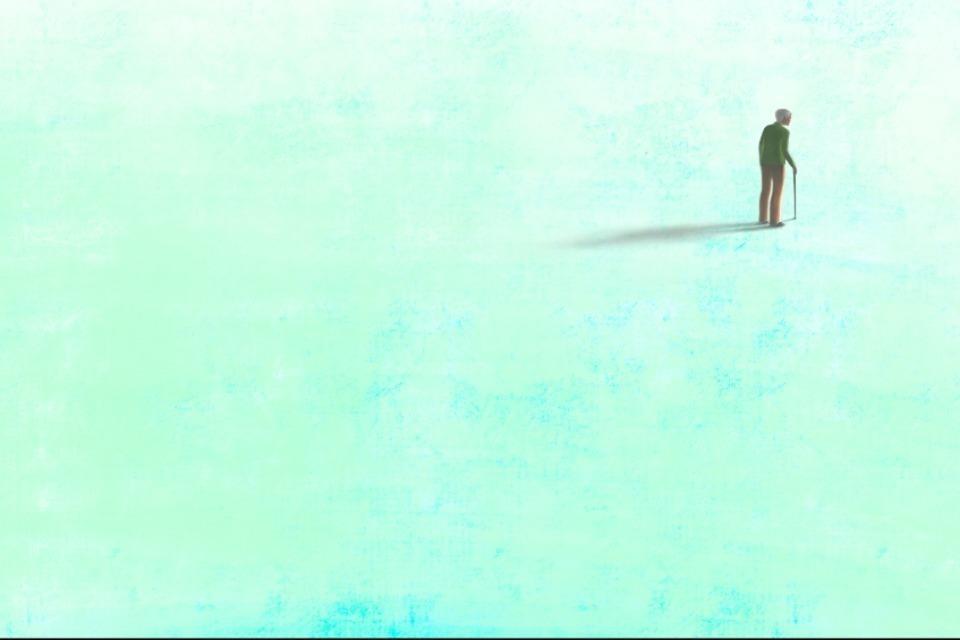

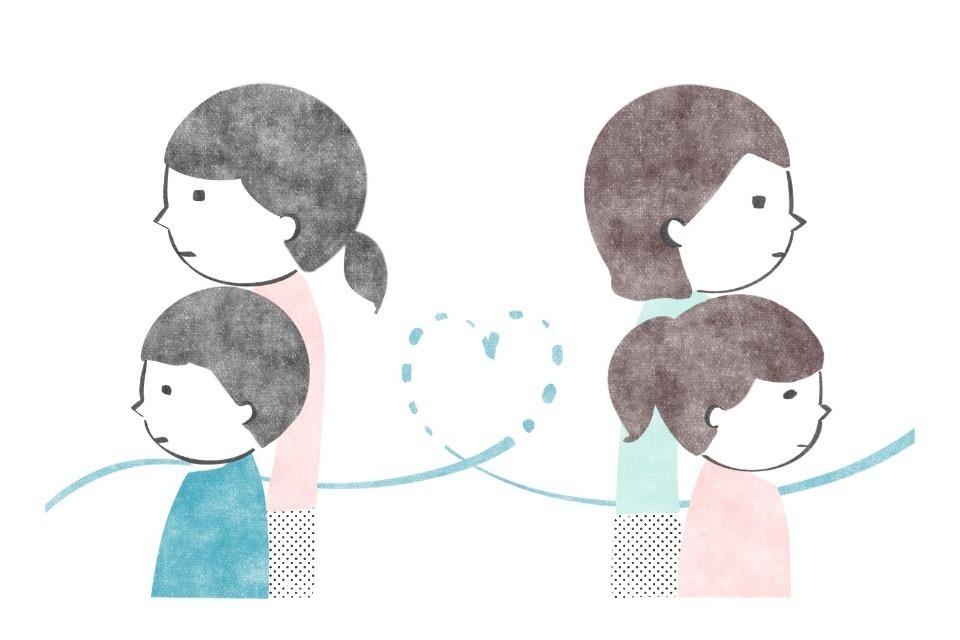
1. 地域社会のつながりの希薄化と孤立の深刻化
都市部への人口集中や核家族化、地域によっては過疎化が進む中で、近所付き合いが減り、住民同士のつながりが薄れてきています。特に、高齢の方、転入された方、障がいをお持ちの方は孤立しやすく、心身の健康に影響を及ぼす可能性があります。災害時には、お互いに助け合う力が弱まることも心配です。
2. 多様化するニーズへの対応の遅れ
高齢化が進むにつれて、介護や医療だけでなく、生活支援、社会参加、移動支援など、高齢の方々のニーズは多様になっています。しかし、移動手段や医療・福祉サービスが不足している地域もあり、課題となっています。また、障がいのある方の社会参加、子育て家庭の孤立、経済的に困っている方への支援など、さまざまな課題が山積しています。現在のサービスだけでは、これらの多様なニーズに十分に対応できていないのが現状です。
3. 制度的福祉サービスの限界
中山間地域や過疎化が進んだ地域では、住民の方々の多様なニーズに対応するため、よりきめ細やかなサービスが必要です。地域によって高齢化の状況など抱える課題が違うため、一律の制度だけでは対応が難しい場合があります。地域の実情に合わせて柔軟なサービスを提供するためには、社会福祉協議会と住民、行政などが連携し、密な協力体制を築くことが大切です。
4. 地域力の低下と住民意識の希薄化
地域活動に参加する人が減り、地域を支える人材が不足しています。特に、若い世代が少ない地域も深刻です。地域を良くしたいという住民の気持ちがあっても、なかなか解決できないことも課題です。行政だけでなく、地域住民や民間団体など、さまざまな立場の人が協力して地域課題を解決していく必要があります。
Why we are tackling this issue



地域福祉の推進
社会的つながりの強化
地域住民の交流を促進し、社会的なつながりを強化することを目指しています。コミュニティの場を提供もしくは、自ら創り出すことを支援することで、住民同士が知り合い、支え合う関係を築くことができます。
孤立防止と支援ニーズの把握
誰でも気軽に集まれる場所を作ることで、高齢者や障がい者、子育て中の親子など、様々な人々が社会とつながる機会を得られます。これにより、孤立を防ぎ、潜在的な支援ニーズを早期に把握することができます。
地域課題の解決
住民主体の課題解決
コミュニティの場を通じて、地域の課題や住民のニーズを直接把握し、住民主体で解決策を考え、実行することができます。
多様な主体の参画と協働
地域の様々な団体、企業、NPOなどが参加し、それぞれの特性を活かして地域課題に取り組むためのプラットフォームとなります。
福祉サービスの充実
新たな福祉サービスの開発
コミュニティの場での交流を通じて、制度外であっても社会的に求められている新たな事業やサービスのニーズを発見し、開発することができます
社会参加の促進
あらゆる人の社会参加
誰もが気軽に参加できる場を提供することで、高齢者、障がい者、子育て中の親子など、あらゆる人々の社会参加を促進します。
ボランティア活動の推進
子育てサロンやこども食堂など、コミュニティの場を通じて、ボランティア活動の機会を提供し、地域住民の社会貢献意識を高めることができます。
これらの理由から、吉賀町社協は「だれでも気軽に集まれるコミュニティの場を作る」ことを重要な活動の一つとして推進しています。この取り組みは、地域福祉の向上と「福祉のまちづくり」の実現に大きく貢献しています。
How support is used



社協会費をはじめとする寄付金は、吉賀町社協の貴重な財源として、高齢者や子ども、障がいがある方などに対する様々な福祉活動の活動資金となります。


