私たちの取り組む課題
【子どもの居場所】
登校以外の選択肢が少ない現状
山形県天童市および近隣市町村では、学校以外の学びの場や居場所が限られているのが現状です。近年、子ども食堂は増えつつありますが、子どもたちが学校の時間帯に過ごせる場所は依然として少ないです。適応指導教室(支援センター)は設置されていますが「学校に行かない」「行けない」ことがまるで悪いことのように感じられ、公的な機関すら利用を躊躇する風潮があります。また、適応指導教室によっては学習を重視した場合も多く、まずはゆっくり過ごしたい、安心しているだけで認めてもらえることを望んでいる子どもたちにとってはハードルが高くなっています。学校以外の選択肢がないことや、登校日数を重視する風潮は、形式的に登校扱いとするために朝や夕方に顔を出すだけ、あるいは週に数回プリントを受け取るだけの状況を生みだします。不登校の時期には自宅でゆっくり過ごすことも大切ですが、同時に社会とつながっていく意味で学校以外の居場所を広げていく必要があると考えています。
【子どもの学びを支える】
発達障害といわれる人数が増え支援学級が増加している現在、放課後等デイサービスの利用に当てはまらない、利用できない児童も急増しています。通常学級の中で多く過ごしているそうした児童は学年が上がるに従い、コミュニケーションがうまくいかずにトラブルになったり、学習における困難さから学力低下に繋がったりします。もっと先を見れば、社会にでてから「適応できず退学、退職」といった現象を引き起こします。放課後の時間を活用し、遊びの中で子どもたちの力を育む学びの支えを行うことが必要と考えています。
【子どもを取り巻く環境を整える】
子どもたちが安心して健やかに成長するためには、保護者の心の安定が不可欠です。保護者が笑顔でいられることは、子どもたちの安心感に直結し、それはひいては企業の働き方に影響していきます。「不登校離職」保護者にとって子どもの居場所がないことは仕事にも影響していきます。(発達障害も同じです)また多忙を極め、多様性を求められる学校の先生方にもサポートが必要な状況です。教室の中に居心地の悪さを感じている子どもたちが教室離脱や不登校につながっていきます。その悪循環を改善するためには外部からのサポートが必要な場合もあります。
なぜこの課題に取り組むか


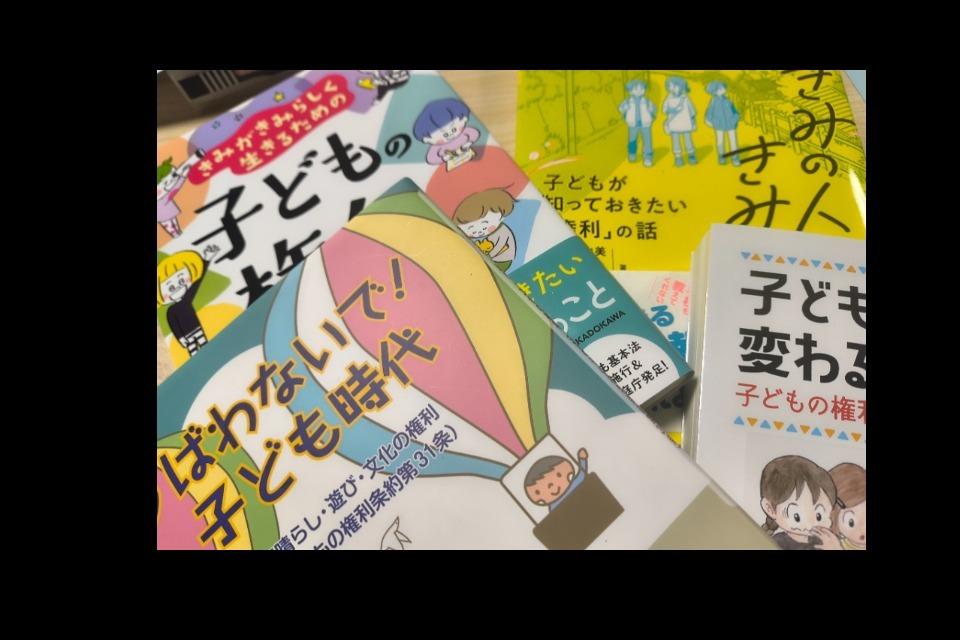
【子どもの居場所】
自分らしくいられる場所の重要性
学校に行かないことが悪いことなのではなく、子どもたち一人ひとりの状況や感情を尊重し、彼らが自分らしくいられる場所を見つけることが何よりも重要です。学校だけが学びの場ではありません。子どもたちは自分のペースで学び、興味のあることに打ち込み、同じような経験を持つ仲間や理解ある大人と出会うことができます。
社会とのつながりの大切さ
不登校の子どもたちにとって、社会とのつながりを保つことは非常に大切です。居場所を見つけることで、孤立感を解消し、安心感を得ることができます。また、多様な背景を持つ人々と交流することで、視野が広がり、新たな価値観に触れる学校とは異なる形で社会とつながることができます。
未来へ向かって
子どもたちが安心して自分らしく過ごせる居場所や学びの場を地域全体で増やしていくことが、これからの社会には不可欠です。学校以外の選択肢が充実することで、子どもたちはそれぞれのペースで成長し、自信を育み、未来に向けて力強く歩んでいくことができるでしょう。
不登校は決して特別なことではありません。すべての子どもたちが、安心して自分らしく過ごせる居場所を見つけ、社会とつながりながら豊かな人生を歩んでいけるよう、地域全体で支えていくことが求められています。
【子どもの学びを支える】
通常の学級や支援学級とは異なる、放課後の少人数での支援は、発達の課題を持つ児童にとって、以下のような対応が必要とされます
- 個別のニーズへの対応: 大人数の中では見落とされがちな個々の学習スタイル、興味、得意なこと、苦手なことにきめ細かく対応できます。
- 得意なことの伸長: 興味のある活動や得意な分野に特化したプログラムを提供することで、自己肯定感を高め、自信を育むことができます。これは、学習意欲全体の向上にも繋がります。
- 生活スキルの習得: 集団生活の中で必要なソーシャルスキルや、自立に向けた生活スキル(例: 片付け、身の回りのこと、コミュニケーションの取り方など)を、個々のペースに合わせてじっくりと習得する機会を提供できます。
- 学習の個別サポート: 学校での学習内容の補習や、つまずきやすいポイントに特化した指導を少人数で行うことで、理解を深め、学習の遅れを取り戻すことができます。また、宿題のサポートなど、家庭での学習負担を軽減する役割も果たします。
- 安心できる居場所: 学校とは異なるリラックスした雰囲気の中で、安心して自分のペースで過ごせる居場所があることは、精神的な安定に繋がります。これにより、ストレスを軽減し、自己表現の場を得ることができます。
- 多様な経験の機会: 普段の学校生活では経験しにくい、創造的な活動や体験活動(例: アート、音楽、プログラミング、工作、料理など)を通じて、新たな興味や才能を発見するきっかけになります。
放課後デイサービスは受給者証がないと利用できません。子どもたちのちょっと苦手に寄り添った支援を行うことは、子どもたちの進路を支えることになります
【子どもを取り巻く環境を整える】
保護者の心の安定が重要な理由
保護者が精神的に安定していることは、子どもたちの情緒の安定に大きく寄与します。保護者がストレスを抱えていたり、不安を感じていたりすると、それが子どもにも伝わり、子どもの行動や精神状態に影響を与える可能性があります。反対に、保護者が心のゆとりを持って子どもと接することができれば、子どもは家庭を安心できる場所として認識し、のびのびと成長できます。
企業の働き方への影響
保護者の心の安定は、企業の働き方にも密接に関わっています。例えば、育児と仕事の両立に悩む保護者が多い現状では、企業が柔軟な働き方(例:リモートワーク、フレックスタイム制、時短勤務など)を提供することで、保護者の負担を軽減し、精神的な安定をサポートできます。これにより、保護者は仕事にも集中しやすくなり、生産性の向上にも繋がります。また、企業が子育て支援に積極的であることは、優秀な人材の確保や定着にも貢献し、企業のイメージアップにも繋がります。
学校の先生方への支援の必要性
保護者の心の安定を考える上で、学校の先生方を支えることも非常に重要です。先生方は、日々の教育活動に加え、保護者との連携、生徒指導、事務作業など多岐にわたる業務を抱えています。学校の中にファシリテーションを取り入れるとともに必要に合わせた伴走支援をすることで、先生方のサポートが必要です。先生方が心身ともに健康であれば、より良い教育を提供でき、それが結果的に子どもたちの安心感、ひいては保護者の心の安定にも繋がるでしょう。
支援金の使い道
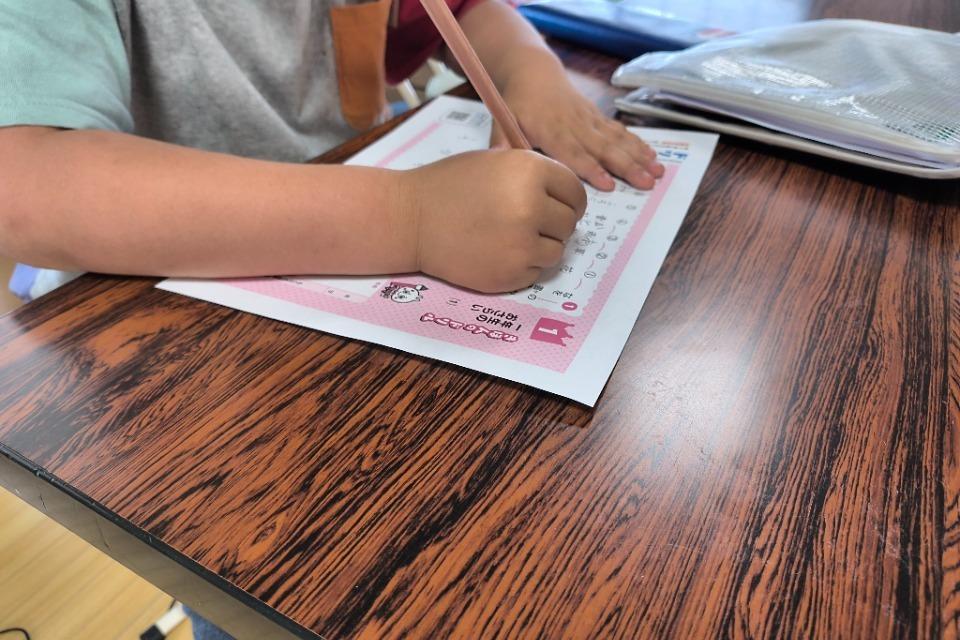


・スクールスタッフ人件費
・家賃・光熱費
・外部講師謝礼
・印刷・通信費


