私たちの取り組む課題
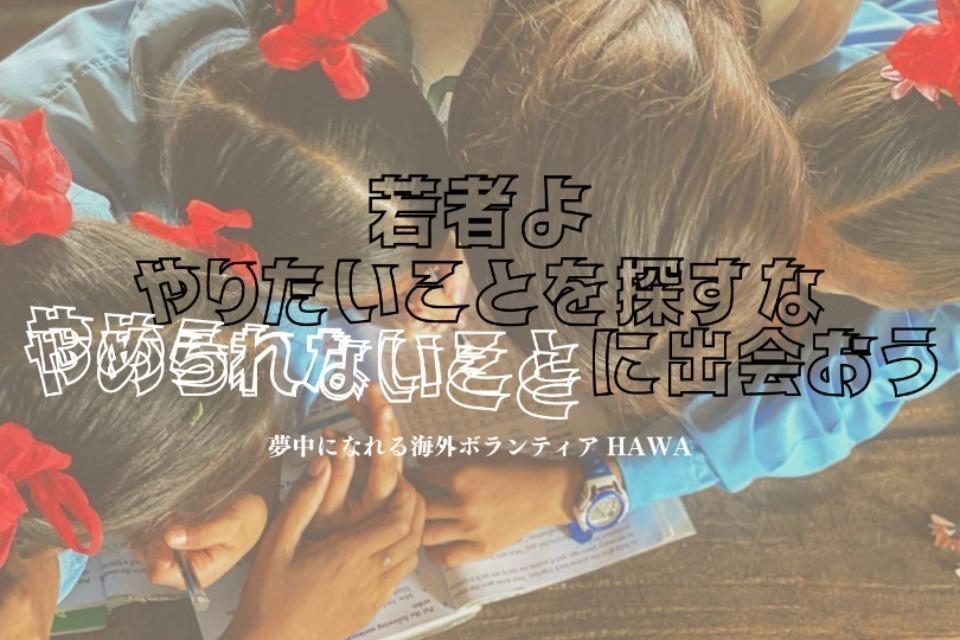
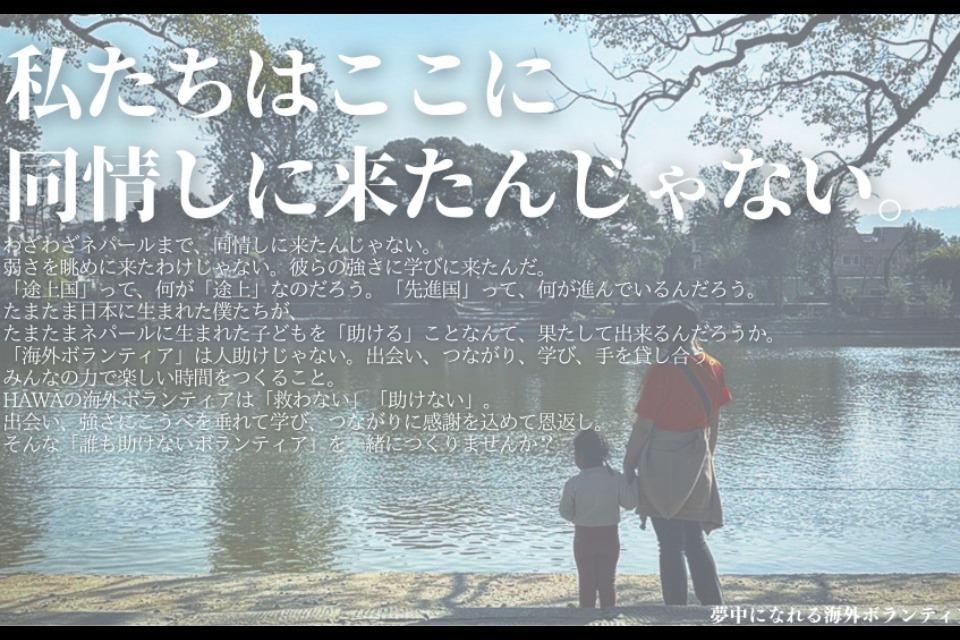

▶︎「貧困」の望まぬ「観光資源化」「商品化」
現在の国際協力、開発支援の現場では、ある部分を全体化させて伝え、「かわいそうな支援対象」とイメージづけることで支援を獲得するような方法が横行しています。しかし、現場は写真一枚の情報よりも複雑であり、シンプルにまとめきれないような感情の構造があります。ボランティアの経験がキャリアアップに繋がることが自明な現代社会において、「かわいそうな子どもたち」を売り物に理想のキャリアを買うような構図が出来上がってしまいました。しかしこれは、従来より指摘されていた貧困の「観光資源化」「商品化」の問題と重なります。
途上国と呼ばれる国の人々を、まるで動物園にいる動物のように、見せ物として扱うことは「声の搾取」と言えます。私たちは、そんな搾取的な構図になってしまった国際協力を現場から変えるために、「新しいボランティアメソッド」の作成に取り組んでいます。より多様な人々に目配せし、さまざまな方法でリスペクトを持って行う強力の方法論を探しています。
▶︎アフタースクールの運営
我々はネパールの首都カトマンズでアフタースクールを運営しています。公立高校に対して人数の少ないアフタースクールでは、子どもひとりひとりの声を拾いながら学習を進めることができます。HĀWĀの運営するアフタースクールでは、子どもの声を通じて家庭内暴力や地域課題の早期発見を行い、自治体の力を通じて解決します。
▶︎ネパール国内の教育格差
「世界最貧国」とも言われたことのあるネパールでは、教育格差が大きな問題になっています。都市部と農村の、私立校と公立校の格差は大きく、十分な教育が受けられない子どもが多くいます。さらに、求められているのは学校教育だけではありません。生理が来た時に半屋外の不衛生な小屋での生活を強いられる習慣や、悪徳業者の留学や海外就労の案内に乗ってしまったために海外で奴隷のような生活を強いられるような事例も多くあります。
▶︎ネパールの人身売買被害者へのケア
インドと国境を接するネパールでは、性的サービスを強要される労働への人身売買が横行しています。「稼げる仕事があるから」という甘い言葉で声をかけて連れらるものの、実際は不衛生な部屋で望まぬ仕事を強要されるような事例が多数あります。その結果として身体や心を壊してしまうことが多々あり、再び自分らしく生きるためには多くのケアが必要になります。
なぜこの課題に取り組むか



HĀWĀは「誰もが自分の人生に夢中になれる社会の実現」を目指しています。この「誰もが」という表現には、今まで国際協力の場で想定されてきた支援「する側」と「される側」という2分法的な立場を乗り越えるという意図が込められています。現に、支援を「する側」とされてきた先進諸国でもさまざまな問題が絶えません。現代社会は経済格差に拘らず、どちらの国に生まれても、サバイブするためにそれぞれの困難があります。
その双方の困難を乗り越えるために、両者が出会う場としての「ボランティア」の在り方を考え直すためのプロジェクトこそHĀWĀなのです。
HĀWĀはネパール語で「風」を意味する言葉です。関わった全ての人の人生に、社会に新しい風を吹き込むために私たちがあります。
支援金の使い道



教育プロジェクト運営経費
いただいた寄付金は子どもたちが学校後に通うアフタースクールのために、知育玩具の寄付や施設の修復を行うためのプロジェクト経費になります。地元の学校や街の住人の方々と協力して炊き出しを行ったり、特別授業を行ったりします。さらに専門の教員を雇うことを目指しています。
アフタースクールでは補足的な学習だけではなく、海外での就労や自分の身を守るための情報を伝えるための特別授業も行います。さらに、日本人の大学生ボランティアを招いて交流・授業を行いながら、外の世界を知るためのきっかけづくりを行います。


