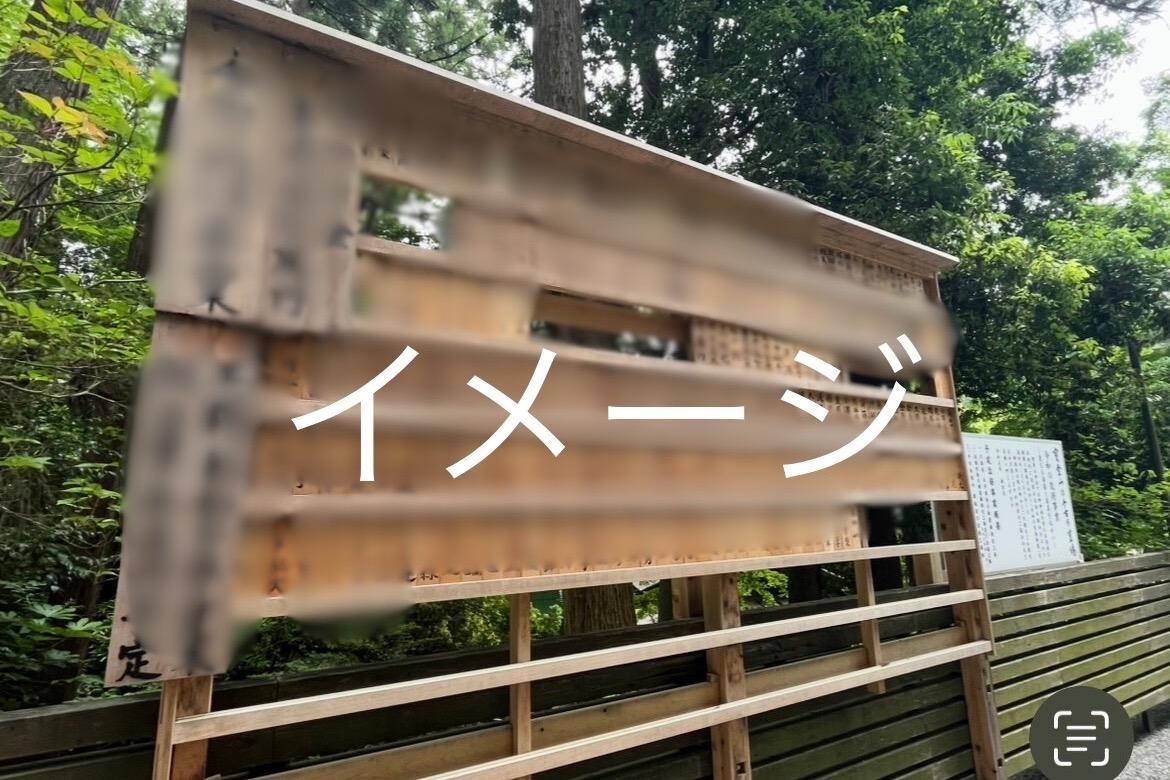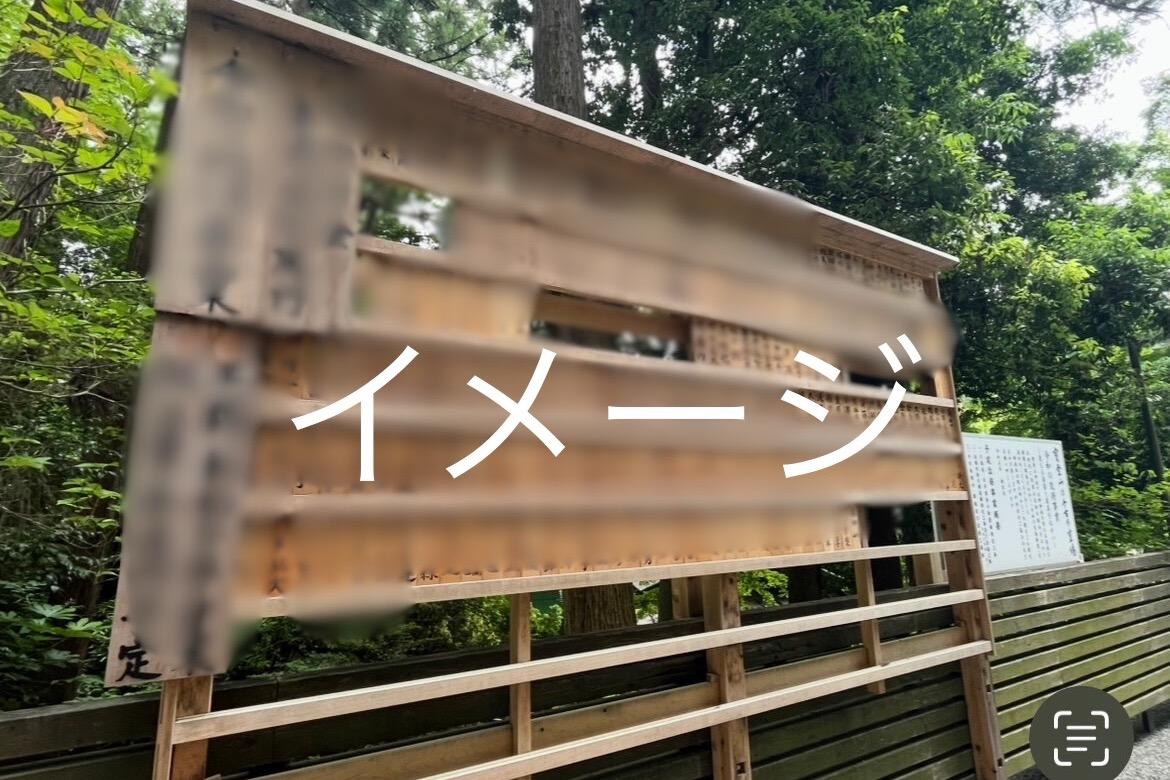千葉県木更津市桜井。この地には、江戸時代から150年以上、地域の人々の祈りと希望を受け止めてきた「負けない神社」(正式名:嚴島神社/桜井水神宮)が存在します。
今、魂を入れる完成のために、“最後の一歩” 300万円が必要です。
この神社は、人生の「ここだけは負けたくない」という瞬間に、何世代にもわたり寄り添ってきました。
受験、就職、家族の健康、商売、困難や悲しみ――そのすべての「負けたくない」気持ちが、この場所に集まり続けてきました。
しかし令和4年、台風と老朽化により、社殿はついに解体されました。
神社の消滅が進む現代。私たちの「心の拠り所」もまた消えていくのか。
その危機を前に、地元有志は「守る会」を結成し、再建への挑戦を始めました。
本プロジェクトは、単なる神社再建ではありません。
困難を「負けずに乗り越える」物語を、未来へ手渡すための挑戦です。
ストーリー
1. なぜ今、「負けない神社」再建なのか
全国の神社は年々減少しています。
2024年現在、日本の神社は78,689社。30年前と比べて2,676社が消えました。
宮司や管理者の不在、高齢化、過疎化、そして経済的困難。神社の消失は、祈りや文化だけでなく、「人が集う場所」「物語の舞台」をも失わせています。
桜井水神宮もその危機に直面しました。

しかしこの地の人々は、「心の支え」を残すため、再建を決意しました。
⸻
2. 「負けない神社」の物語――林家と村人たち、再生をつなぐ歩み
■ 水とともに生きてきた土地のはじまり
桜井の地は、目の前に海、背後に山を抱えた田畑のひろがる土地でした。

豊かな反面、毎年のように水害や干ばつと向き合いながら生きてきました。
水がもたらす恵みと脅威。
大雨で田畑が流される日もあれば、川が枯れてしまう夏もありました。
嵐で船が流されることもありました。
そんな土地で生きる人々が大切にしてきたのは、「勝つ」ことではありません。
「どうか、負けないように」。
自然に打ち勝とうとするのではなく、受け入れ、知恵を寄せ合い、何度倒れてもまた立ち上がる。
そうやって村の人たちは助け合い、支え合いながら暮らしてきました。
やがて村の中央に小さな祠が建てられます。
水の神・市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)を祀るこの祠こそが、「負けない神社」の始まりです。
季節の節目や災害のたびに、村人たちが集まり、静かに手を合わせてきました。
海での安全を祈願し、海の恵みに感謝を捧げる欠かせない場所にもなりました

その祈りは「勝ちますように」ではなく、「負けないでいられますように」という素直な願いでした。
⸻
■ 江戸時代――林家と「負けない」の精神
江戸時代になると、桜井は上総国請西藩の領地となります。
この小さな藩を治めていたのが林家でした。
 林家は、領主でありながら村人とともに畑に立ち、日々の暮らしを共にしていました。
林家は、領主でありながら村人とともに畑に立ち、日々の暮らしを共にしていました。
第六代藩主・林忠旭(はやし ただあきら)は、飢饉や災害が続く苦しい時代、
「勝つ」ことよりも「負けない」ことを選び取った人物です。
自分の俸禄を投げ出し、種籾や食糧を村人に分け与え、自ら泥にまみれて田植えもしました。
「勝つことより、一人でも多く負けないでほしい」そんな言葉が、村人の心を支え続けました。
やがて林忠旭公は、村の復興の象徴として、桜井水神宮の社殿再建に取り組みます。
解体時に見つかった棟札「再造立水神宮為天下泰平 林播磨守」は、

左から:当時書かれていた文字輪郭、右下に書かれていた林播磨守の文字輪郭、赤外線で撮影した表面と裏面、表面の拡大写真
権力や誇りを示すものではなく、「すべての人の暮らしが絶えないように」という
温かい願いが込められています。
この時代、神社は単なる祈願所ではなく、
「負けない」心を支え、家族や隣人、村全体の絆をつなぐ場所でした。
⸻
■ 幕末から明治――林忠崇の決断と帰農、伝わる負けない精神
時代が大きく動いた幕末、林家はさらに難しい選択を迫られます。
第七代藩主・林忠崇(はやし ただたか)は、わずか二十歳で家督を継ぎました。
徳川幕府の崩壊、戊辰戦争――
忠崇は、徳川家への忠義を守るか、領民の暮らしを守るかで苦悩しました。
義を貫き出陣した当日、この神社の前を通り祈りを捧げたと伝えられています。

 最後には、名誉も家禄もすべて捨てて「藩主を辞し、藩そのものを返上」し、
最後には、名誉も家禄もすべて捨てて「藩主を辞し、藩そのものを返上」し、
自ら田畑を耕す道、すなわち帰農を選びました。
「刀も鍬も同じ。どんなときも人のために汗を流すことが、自分の役目だ」
その後、明治維新の流れの中で忠崇は華族に列せられましたが、
権威に執着せず、土地と人を見守り続けました。
林家のこうした「負けない」精神は、
ただ武力や名誉に頼るのではなく、何度でも立ち上がり、
自分にできることを淡々と、誠実に積み重ねるという“やさしい強さ”です。
この想いが村人たちに受け継がれ、神社の歴史のなかにも静かに息づいています。
⸻
■ 「負けない伝説」としての神社
明治時代、桜井の地を大火が二度襲いました。
火事の夜、村人たちは「せめて神社だけは」と身を挺して水をかけ続けました。
火の手が迫るなか、風向きが変わり、神社だけが焼失を免れた――
これは「炎の伝承」として今も語り継がれています。
この出来事は、
「火を止める神社」「赤(火や赤字)を出さない負けない神社」として村人の心に刻まれ、「どんな困難でも負けずに守り抜く」象徴となりました。
⸻
■ 龍の彫刻―地域の誇りと“負けないご利益”
神社本殿には、江戸から明治にかけて彫られた三体の龍があります。

名工・後藤派の職人による昇龍と降龍は、
村人たちが「龍だけは何があっても残す」と守り抜いた存在です。
災害や修理のたびに協力して修復し、龍に手を合わせてきました。
この龍は、地域の誇りであるだけでなく、
「水を呼び、火を払い、災いを跳ね返す」負けない力の象徴として、
村人に安心と勇気を与えてきました。
⸻
■ 家族と地域をつなぐ“心の拠り所”
神社は、祭りや日常のなかで「もう一度立ち上がる勇気」をもたらしてきました。
家族の節目、子どもの誕生、受験、結婚、別れ。
「この場所があったから、また頑張ろうと思えた」
そんな思い出が、何世代にもわたり重なっています。
昭和の戦争と復興の時代も、
「負けたくない」「家族を守りたい」と
多くの人が神社に祈り、再び歩き出す力をもらいました。
⸻
■ 現代につながる「負けない心」
バブル崩壊、リーマンショック、経済の不安や社会の変化。
今も、合格祈願や商売繁盛、健康長寿など、「どうしても負けたくない」と願う人がこの神社に集い続けています。
現代の「負けない神社」には、勝つことだけを願うのではなく、
「負けないで、また歩き出せる力」を分かち合う温かな文化があります。
⸻
◎ 「勝つこと」よりも「負けないこと」
この神社の歴史が教えてくれるのは、「勝ち続ける」ことよりも、
「何度でも負けずに立ち上がること」の大切さです。
人生には、どうしても勝てない場面もあります。
でも、負けずにもう一歩進めば、また未来が開ける――
その“やさしい強さ”を、この土地と神社は、世代を超えて伝えています。
「どんな困難も、決して心が折れない場所」
「失敗しても、また歩き出せる勇気をもらえる場所」
それが、“負けない神社”です。
⸻
3. 現代の危機と再建への挑戦
令和四年、台風被害と社殿の老朽化により、桜井水神宮は解体を余儀なくされました。
 地域の人々にとって大きな喪失――。
地域の人々にとって大きな喪失――。
「このままでは負けない神社の歴史も、祈りも絶えてしまう」
そう感じた地元有志は、町内会長を中心に「守る会」を立ち上げます。
最初はたった二人での活動。資料を集め、古老や遠方の支援者に話を聞き、一軒一軒地元を回って「この神社の意味」「林家や村の歴史」「負けない心」を丁寧に伝えました。
寄付を呼びかけ、地域の絆をもう一度つなぐために奔走しました。 その努力が少しずつ実を結び、2025年5月には180件、1,223万円のご支援が集まりました。
その努力が少しずつ実を結び、2025年5月には180件、1,223万円のご支援が集まりました。
この力で新社殿の基礎工事が始まり、建設が進み、美しい銅板葺き屋根が完成。
 「この神社は、みんなで守るもの」――その思いが世代を越えて広がっています。
「この神社は、みんなで守るもの」――その思いが世代を越えて広がっています。
しかし、目標金額は3,000万円。
完成にはあと1,500万円のご支援が必要です。
⸻
4. 今、必要な“最後の一歩”―魂を入れる完成へ
新社殿は立ち上がりましたが、「負けない神社」として本当の完成には“最後の仕上げ”が必要です。
• 広島・嚴島神社からの御分霊勧請(御霊入れ神事)
• 境内を守る玉垣設置(ご支援者名を刻む永年顕彰)
• 参道・手水舎・植栽・歴史解説板・照明などの境内整備
• 江戸期龍の彫刻の修復と再設置
これら“魂を入れる最後の仕上げ”のため、残り1500万円が必要です。それも今まで通り地道に支援を募り頑張っていきます、が、目前に迫った【御霊入れ神事関連費用(嚴島神社よりの御分霊、祭典準備、設営)•••約300万円】が頭の痛いところで、今回ご覧いただいたみなさまにご支援お願いできないかとクラウドファンディングを決意した次第です。

⸻
5.ご寄付の使い道
今回のキャンペーンでは、 広島・嚴島神社からの御分霊勧請(御霊入れ神事)及び玉垣設置のための費用300万円として、大切に活用させていただきます。
・嚴島神社よりの御分霊初穂料等費用として40万円
・竣工式(御霊入式)祭典設営等費用として20万円
・玉垣(大9本、小40本)設置等費用として240万
6.最後に―みんなの“負けない物語”を未来へ
「負けない神社」は、誰かひとりのものではありません。
この地に生きるすべての人、そしてまだ見ぬ未来の誰かのための祈りの場所です。
人生には、どうしても「負けたくない」瞬間があります。
苦しいとき、家族や友人の無事を祈るとき、
再起を誓うとき――
この神社は、その“もう一歩”をそっと支えてきました。
「勝つこと」よりも「負けないで、何度でも立ち上がること」。
それがこの土地と神社が世代を超えて大切にしてきた“やさしい強さ”です。
今、皆様の力が「最後のピース」となります。
300万円――どうか、ご支援・応援・SNSでの拡散にご協力ください。
あなたの“負けない物語”と、林家や村人の歴史を重ね、
未来の子どもたちにこの場所を手渡しましょう。
⸻
お問い合わせ・SNS
守る会(担当:鶴岡)090-3918-6481
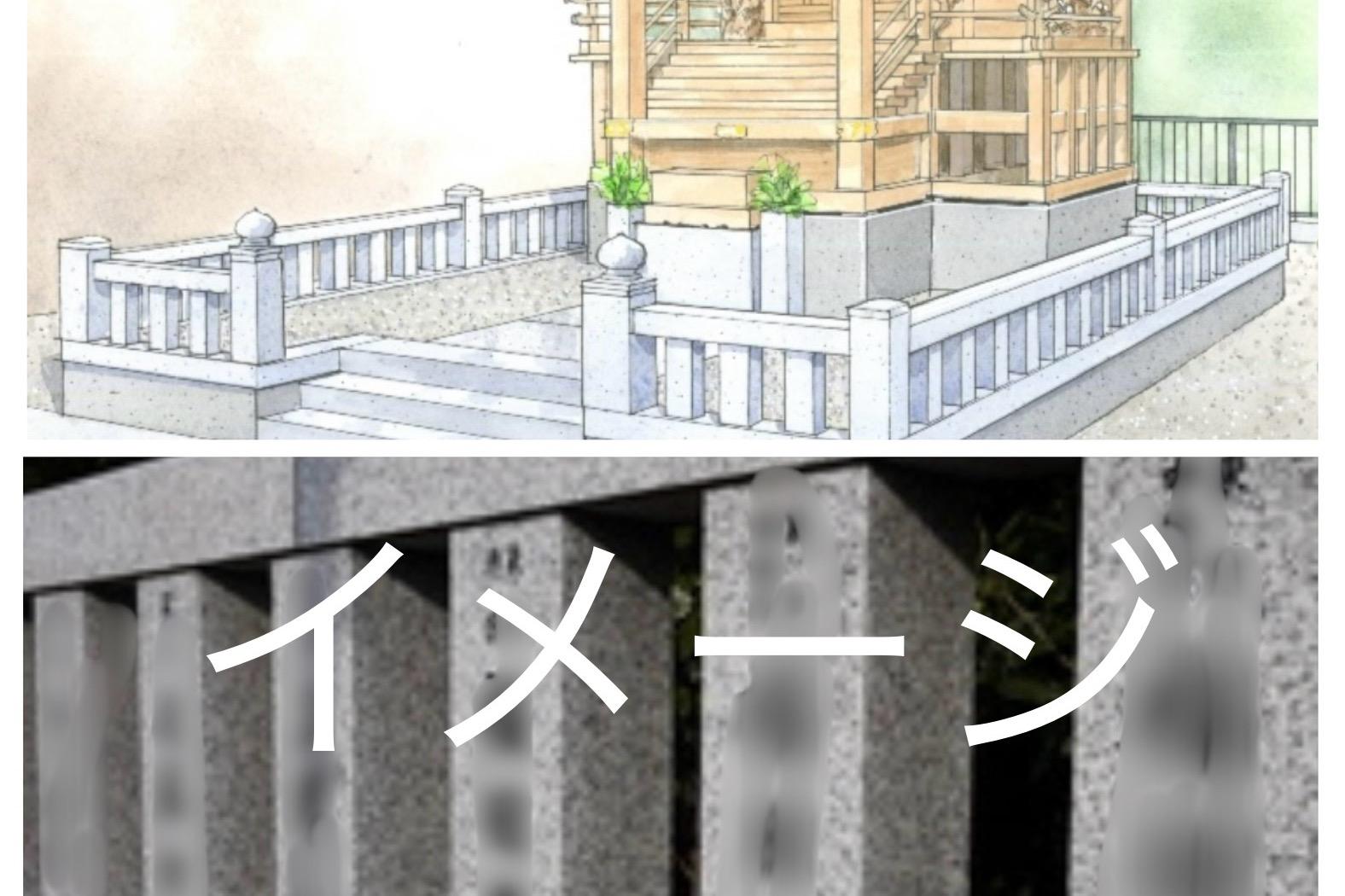
境内玉垣(小)への刻銘【限定40名or40社】+記念品
500,000円
100000円コースに加え、
社殿の台座の玉垣に、
お名前をさせていただきます。
なお、玉垣(大)への刻銘は、
1,000,000円以上とさせていただきます。